特別支援学級を選ぶメリット・デメリット
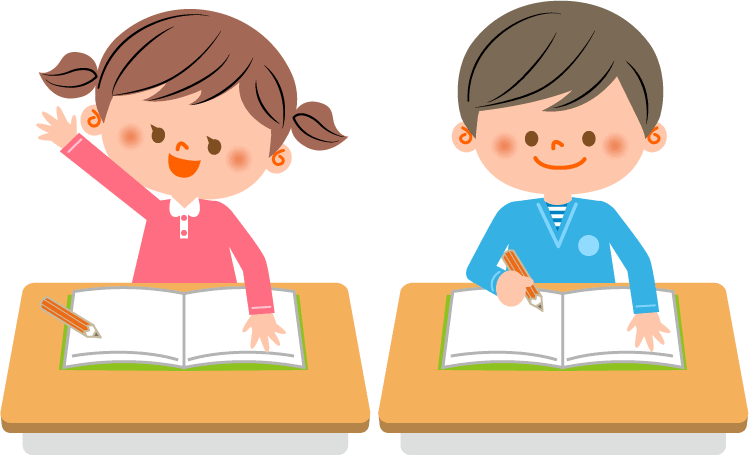
このように、 それぞれの進路には特徴があるので、 お子さんの意思を尊重して決めていくといいでしょう。 学校見学の前には、お子さんの障害についてまとめたものを持参し、教頭先生(できれば校長先生や支援級や通級を担任している先生とも)と面談すると良いでしょう。
3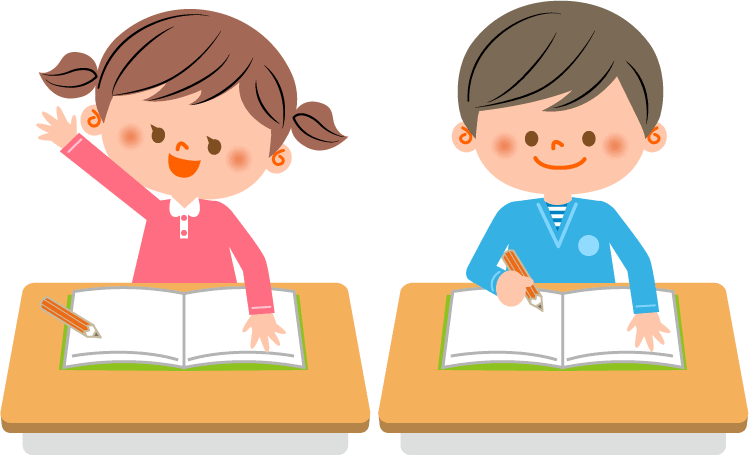
このように、 それぞれの進路には特徴があるので、 お子さんの意思を尊重して決めていくといいでしょう。 学校見学の前には、お子さんの障害についてまとめたものを持参し、教頭先生(できれば校長先生や支援級や通級を担任している先生とも)と面談すると良いでしょう。
3
ここでは、通常の学級とほぼ同様の授業内容・授業時間を定められますが、子どもの病状や発達段階等に応じて下学年・下学部の教育内容が指導されることがあります。 入学希望者が募集定員を上回る場合は、不合格になってしまうことも。

(4) 特別支援学級の種類 特別支援学級は、障害の種類によって弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症・情緒障害の7種類の学級が設置されています。

複数の教師が担任を受け持ち、常時介助員が2~4名ついています。 また、このような交流及び共同学習は、学校卒業後においても、障害のある子供にとっては、様々な人々と共に助け合って生きていく力となり、積極的な社会参加につながるとともに、障害のない子供にとっては、障害のある人に自然に言葉をかけて手助けをしたり、積極的に支援を行ったりする行動や、人々の多様な在り方を理解し、障害のある人と共に支え合う意識の醸成につながると考えます。
9
また、学校において、交流及び共同学習や障害のある人との交流を行うことは、近い将来に社会を担う子供たちの「心のバリアフリー」を育むだけでなく、子供たちを通してその保護者や活動に関わる関係者の障害者に対する理解を促進し、ひいては社会全体の意識を変えることにつながります。

その結果、定期試験でいままで取ったことがないような高得点をとってくれました。 反抗期が激しく親と食事すらとらない子が、5教科合計481点獲得• なお、、教科等を合わせた指導とは具体的には以下のようなものがあります。 また、子どもの個人差を考慮し、個別指導やグループ指導といった授業形態を積極的に取り入れたり、教材・教具の開発・工夫を行ったりするなどの配慮が行われています。

乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画である点が「個別の指導計画」との違いです。 1926年 ・八名川尋常小学校に吃音学級設置 最初の言語障害特殊学級。 2以下であると、通常の授業では困難を来します。