古今著聞集小式部内侍が大江山の歌の事で質問です。現代語訳についても調べて、よ...
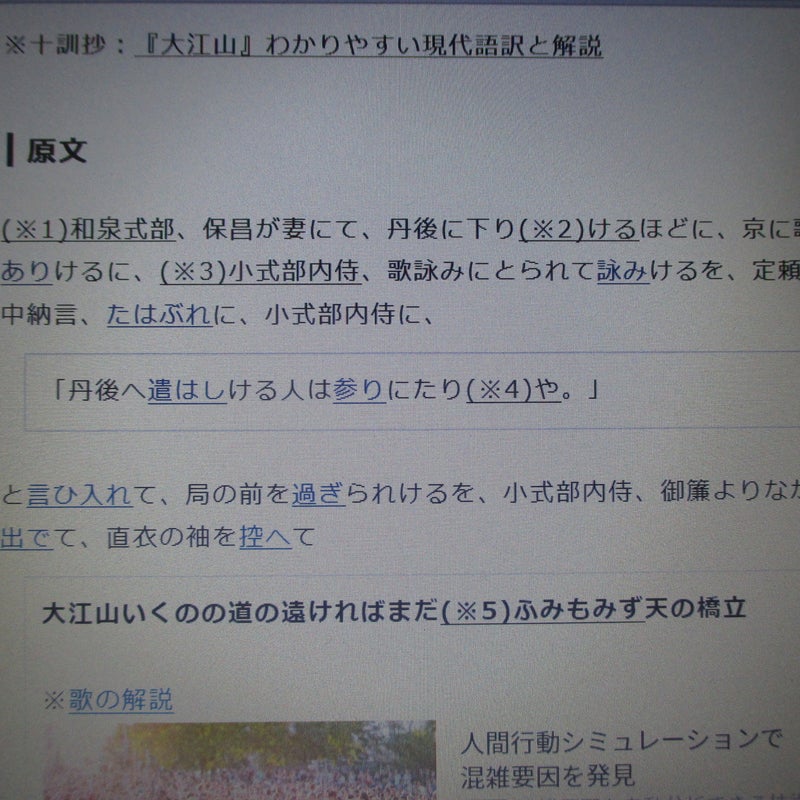
いかに心もとなくおぼすらん。 違う科目の授業を受けているような印象を受けると思います。
12(手段・用法)~で。 大江山 【注1】 いくの 【注2】の道 の 【注3】 遠けれ 【注4】ば まだ ふみ 【注5】も みず 【注6】 天の橋立 【注7】 と 詠みかけけり 【注8】。 (経過点)~を通って。
8
皆さん勉強お疲れ様です、laviclassの管理人です。 そのような状況下で小式部内侍は、定頼の中納言に「歌の名人であるお母さんに、代わりに歌を詠んでもらうために遣わした者は帰ってきましたか。 と詠みかけ けり。
19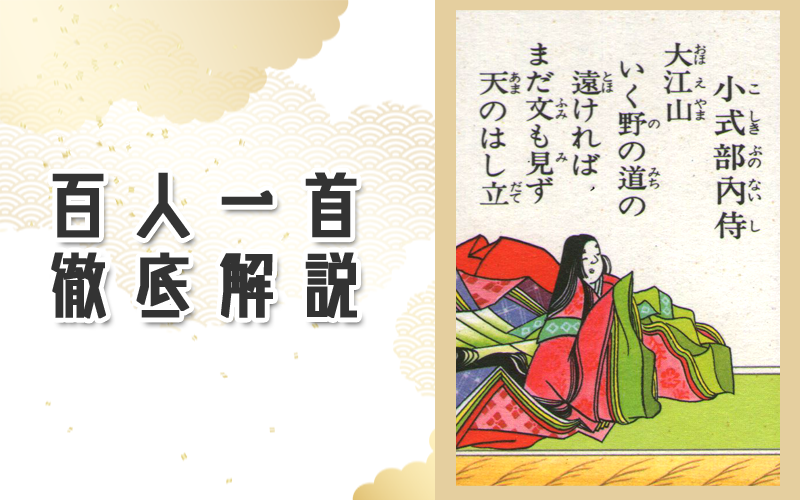
直後に接続が連用形である助動詞「に」が来ているため、連用形となり「出で来(き)」と読む。
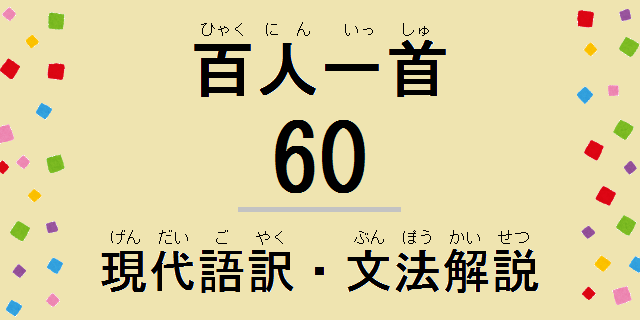
これはうちまかせての 理運のこと なれ ども、 理運=名詞、物事が理にかなっていること、道理、自然。 意味は「~が」。 【本文】 和泉式部、保昌が妻にて、丹後に下りけるほどに、京に歌合ありけるに、小式部内侍、歌詠みにとられて、 詠みけるを、定頼中納言はぶれて、小式部内侍ありけるに、「丹後へ遣はしける人は参りたりや。
8
スタディサプリはプロが録画した講義映像を見ることで学習するものです。 )」とだけ言って、 返歌にも及ばず、袖を引き放ちて 逃げ られ けり。 小式部、これより、歌詠みの世におぼえ出で来にけり。
16
どんなに待ち遠しく思いなさっているだろうか。 (定頼は、小式部内侍が即興ですぐれたこの歌を詠んだのを)意外だと驚いて、 こ =代名詞、これ、ここ は =係助詞 いかに =副詞、どのように、なぜ かかる =連体詞、このような、こういう やう (様)=名詞 や =疑問・反語の係助詞、結び(文末)は連体形となる。

しつれーな奴だと思わない?。 「ふみ」が掛詞となっており、「踏み」と「文」が掛けられている。 過去の助動詞「けり」終止形 小式部、 名詞 これ 代名詞 より 格助詞 歌詠み 名詞 の 格助詞 世おぼえ 名詞 出で来 カ行変格活用動詞「出で来」連用形 に 完了の助動詞「ぬ」連用形 けり。
8