織田信長も言った「是非もなし」とは?意味や使い方を徹底解説!

「是非」は「良いことと悪いこと」や「道理があることとないこと」という意味があり、「なし」という言葉が後続について「是非」を否定する意味合いとなります。 2.しかし、ここで使われる「もと」とは「土台」の意味になります。
13
「是非」は「良いことと悪いこと」や「道理があることとないこと」という意味があり、「なし」という言葉が後続について「是非」を否定する意味合いとなります。 2.しかし、ここで使われる「もと」とは「土台」の意味になります。
13
その当時「是非なし」の意味は多く、「仕方がない」の他にも「当然」や「ひたすら」という意味でも使われていましたが、現在は「仕方がない」の意味だけが残りました。 「是非」には 「物事の善し悪しを区別して判断・批評すること」の意味合いがありますが、 「可否」の言葉にはそういった善悪の判断や批評といった意味までは含まれていません。 相手が明智光秀であれば それまでの二人の関係などから 「仕方がない」、もしくは薄々 「分かっていた」といった意味で使った言葉だという解釈が一般的のようです。
18
A ベストアンサー アメリカに35年半住んでいる者です。 「是非もなし」の意味 「是非もなし」という言葉は、 「是非」と 「なし」という二つの言葉が合わさった言葉になります。 「あまり感心できない事件ですね」と言っているのです。
6
しかし、織田信長の発言後の明智軍への抵抗をみると、「是非もなし(仕方ない、諦めよう)」ではなく、「是非にも及ばない(仕方ない、戦うしかない)」という意味だったのかもしれません。
7
「是非」の意味や使い方 「是非 ぜひ 」という表現は、 「よいことと悪いこと 善悪 ・正しいことと正しくないこと」を意味しています。 (是非を判断する) 「是非」は英語で表現すると、文脈によって使用する単語が異なります。
12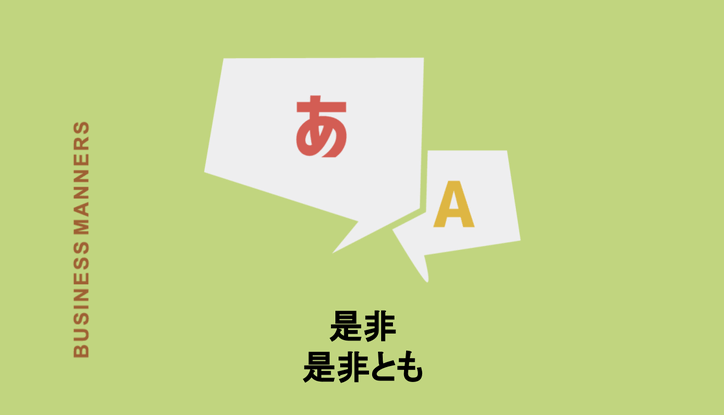
信長は、周囲の戦国大名たちと争いながら領土を広げ、やがて本拠地を安土城に移していきます。 。 本能寺の変で織田信長を急襲した明智光秀は、当時ポルトガルから日本に来ていた宣教師によって、策略家で頭が良いと評されていました。
では、以下の表で「是非もなし」と「是非に及ばず」の違いを確認してみましょう。 「どうしても無理と言われるのでしたら、それは是非もないことです。 ・是非もなく対応せざるを得なかった。
16