請負に関する民法改正のポイント
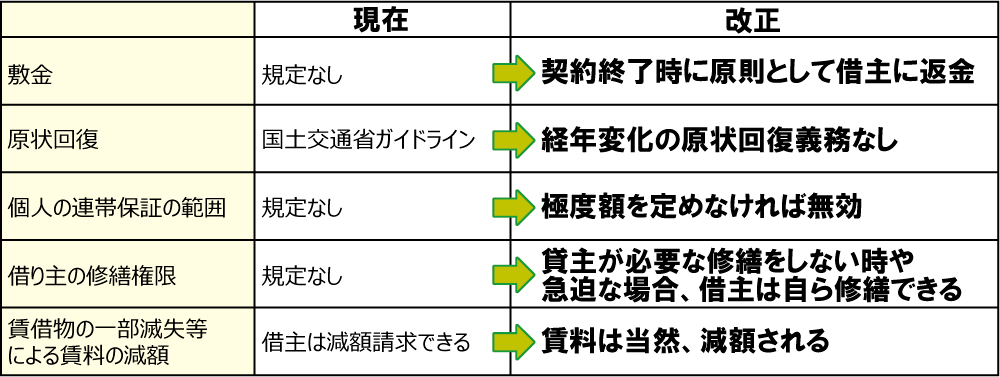
特に譲受人が金融の専門機関などであった場合、譲渡禁止特約の存在を知っていたか知らなかったことについて重大な過失があったことを立証することは困難ではありません。
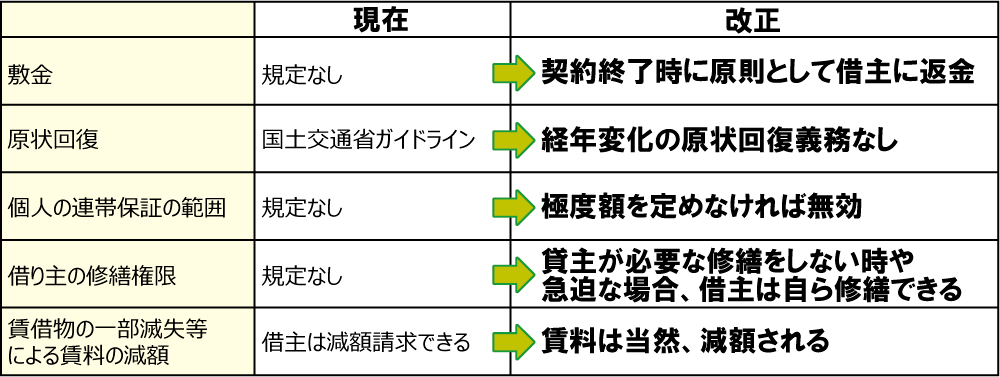
特に譲受人が金融の専門機関などであった場合、譲渡禁止特約の存在を知っていたか知らなかったことについて重大な過失があったことを立証することは困難ではありません。
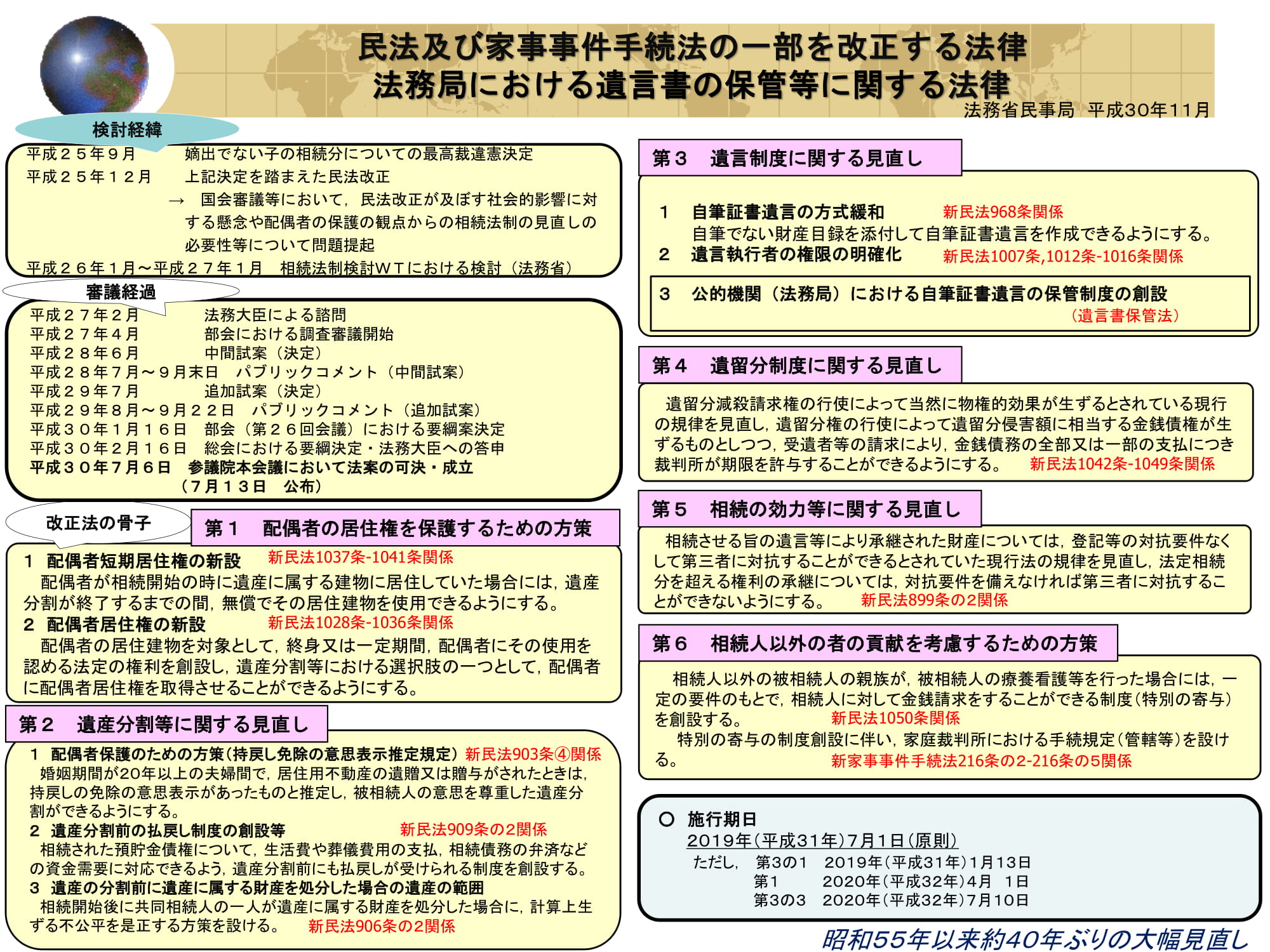
また、判例も、請負契約の目的物であった建物に重大な瑕疵があるため建て替えを要する場合に、注文者は建替費用相当額の損害賠償を請求できるとして、工作物の除去を前提とする判断を下したものもありました。
16
1つ目は、帰責事由の有無の判断については、「 契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」行うということです。 差押え (改正466条の4) 譲渡制限特約により差押禁止財産を作り出すことはできないという判例が明文化されました。 経過措置について 施行日(令和2年4月1日)前に取り消すことができる行為がされた場合は、改正後の125条は適用されず、改正前の125条の適用になります。
18連帯保証人になってくれる人がいない、親や子、兄弟に迷惑を掛けたくないなどの理由で保証会社を利用する人が増えていますが、今後は債務保証の観点から、大家さん側から保証会社による保証を求められるケースも増えるかもしれません。 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
9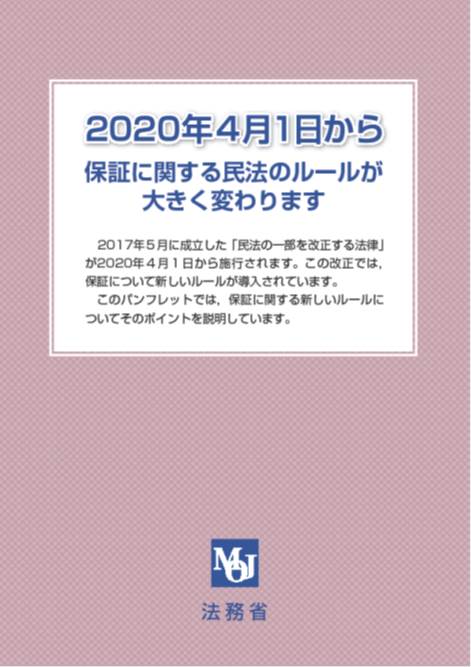
なお、住宅等の瑕疵に関する期間制限に関しては、住宅の品質確保の促進等に関する法律における定めが別途適用されることに注意が必要です。 改正後に新しく加わった救済手段は、追完請求、代金減額請求の二つです。 ところが、古い判決ですが、大審院判決大正12年6月11日が、 法定追認は、取消権が存在することを知らなくても適用されると判示していました。
11
代わりに、債務の不履行につき債権者に帰責事由がある場合には、契約解除ができないことが明記されました(改正民法543条)。 なお、差し押さえたのが悪意・重過失の譲受人なら、債権譲渡が無効ゆえに譲受人は「債権者」に当たらず、差押えが奏功しないと考えられています。