5分でわかる『土佐日記』!作者や内容、冒頭についてわかりやすく解説!
かれこれ、知る知らぬ、送りす。 ある人が、任国(地方官勤務)の四、五年(の任期)が終わって、習わしの(事務引継ぎなどの)ことなどもすっかり済ませ、離任証明の書類などを受け取ってから、(今まで)住んでいた官舎から出て、船に乗ることになっている場所へ移る。 ・酔っぱらって足元がふらついて、足跡が交差して「十」という文字になっている。
10かれこれ、知る知らぬ、送りす。 ある人が、任国(地方官勤務)の四、五年(の任期)が終わって、習わしの(事務引継ぎなどの)ことなどもすっかり済ませ、離任証明の書類などを受け取ってから、(今まで)住んでいた官舎から出て、船に乗ることになっている場所へ移る。 ・酔っぱらって足元がふらついて、足跡が交差して「十」という文字になっている。
10
平穏だ。 しきりに=副詞、同じことが繰り返して起こるさま、しばしば とかく=副詞、あれやこれやと つつ=接続助詞、反復・継続の意味 ののしる=ラ行四段動詞「ののしる」の連体形、大声で騒ぐ、大騒ぎする ぬ=完了の助動詞「ぬ」の終止形、接続は連用形 この数年間親しく交際していた人々が、別れをつらく思って、一日中、あれこれしながら、大声で騒いでいるうちに、夜が更けてしまった。 ある年(934年)の12月21日の、午後八時ごろに、出発する。
18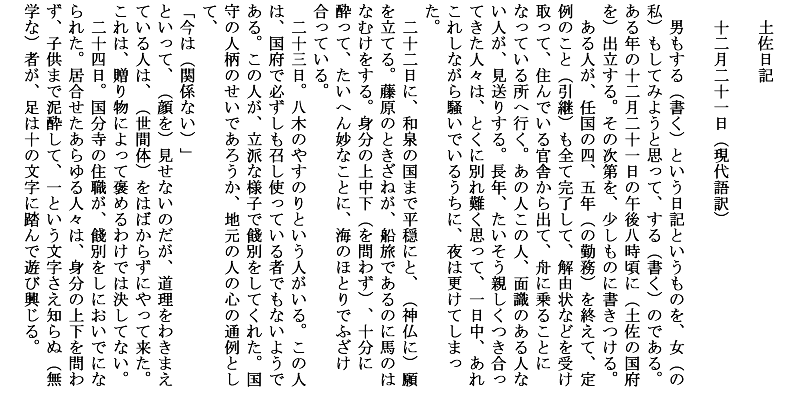
・都に帰った年だから明確になっているはずであるが、曖昧にすることによって単なる記録でなく一般性を持たせ、文学的にする。 ・ なり … 助動詞「なり」の意味は「断定」 ・ 「断定」の「なり」は「連体形」に接続する それの年の十二月の二十日あまり一日の戌の時に、門出す。
5
二十四日(はつかあまりよか)。 ここは「(願)を立つ」なので他動詞。

ある人が、国司としての四、五年の任期が終わって、きまりになっている国司交替の際の 事務引き継ぎのことをすっかりすませて、解由状(=新任者が前任者の任務完了を証明した 公文書)などを受け取って、住んでいる官舎から出て、船に乗る予定の場所へ行く。 この部分ではよく「面白さはなにか」ということを聞かれます。 旅の途中、景色の美しいとある場所を船が通りかかったのだ。

『土佐日記』は紀行文と似ており、日々起きたことが日記のような形式で綴られています。
5 「ものによりて」とはどういうことか。 ある人、県の四年五年はてて、例の事ども皆し終えて、解由など取りて、住む館より出でて、船に乗るべき所へ渡る。 1 「あざる」の意味を説明する。