平家物語『能登殿の最期』(1)解説・品詞分解(平教経vs源義経in壇ノ浦)
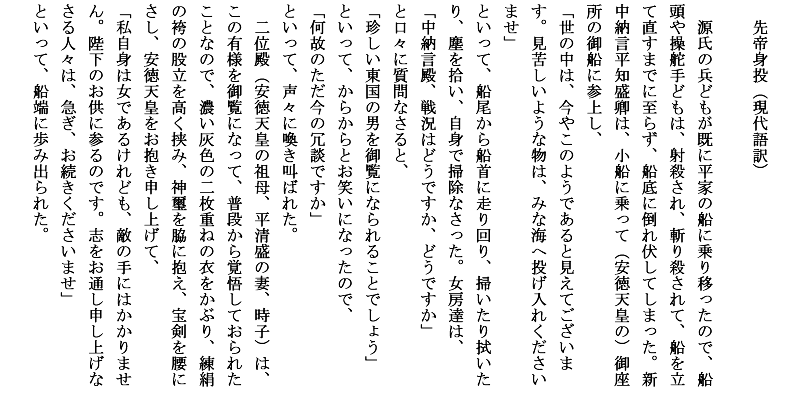
源氏は三千余艘の船なれば、勢の数さこそ多かりけめども、処々より射ければ、いづくに勢兵ありともおぼえず。
17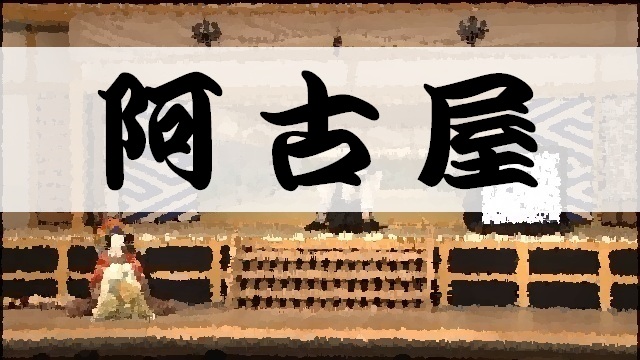
日本一の馬鹿野郎め• およそあたりを払つてぞ見えたりける。 熊野、源氏につく 源平合戦の初期、治承4年(1180年)ののときには、熊野別当の新宮家と田辺家が対立し、源氏寄りの新宮・那智勢と平氏寄りの田辺・本宮勢とに分かれて戦った熊野ですが、熊野別当田辺家の湛増は熊野三山の融和を図り、元暦元年(1184年)10月、湛増が第21代熊野別当に補任(ぶにん)されました。
2
梶原には土肥次郎つかみつき、両人手をすッて申しけるは、「是程の大事をまへにかかへながら、同士戦候はば、平家ちから付き候ひなんず。 おっしゃる。 あきれたる御有様にて、「尼ぜ、我をばいづちへ具して行かむとするぞ。
14
壇ノ浦夜合戦記• 主上今年は八歳にならせ給へども、御年のほどよりはるかにねびさせ給ひて、 主上(=安徳天皇)は今年は八歳におなりになったけれども、ご年齢のわりにははるかに大人びていらっしゃって、 御かたちうつくしく辺りも照り輝くばかりなり。 これほどの一大事を前にしながら同士討ちなどしていては、平家に勢いづかせてしまいます• 「白旗(しらはた:源氏)につけ」との権現の仰せを、なお疑って、白い鶏7羽と赤い鶏7羽を、権現の御前で勝負させる。 沖では平家が、海一面に舟を並べて見物している。
10
長枕辱合戦(作品社、昭和二十七年三月)• 伝説によると鉄製の烏帽子甲(えぼしかぶと)をかぶって戦いに臨んだといいます。
10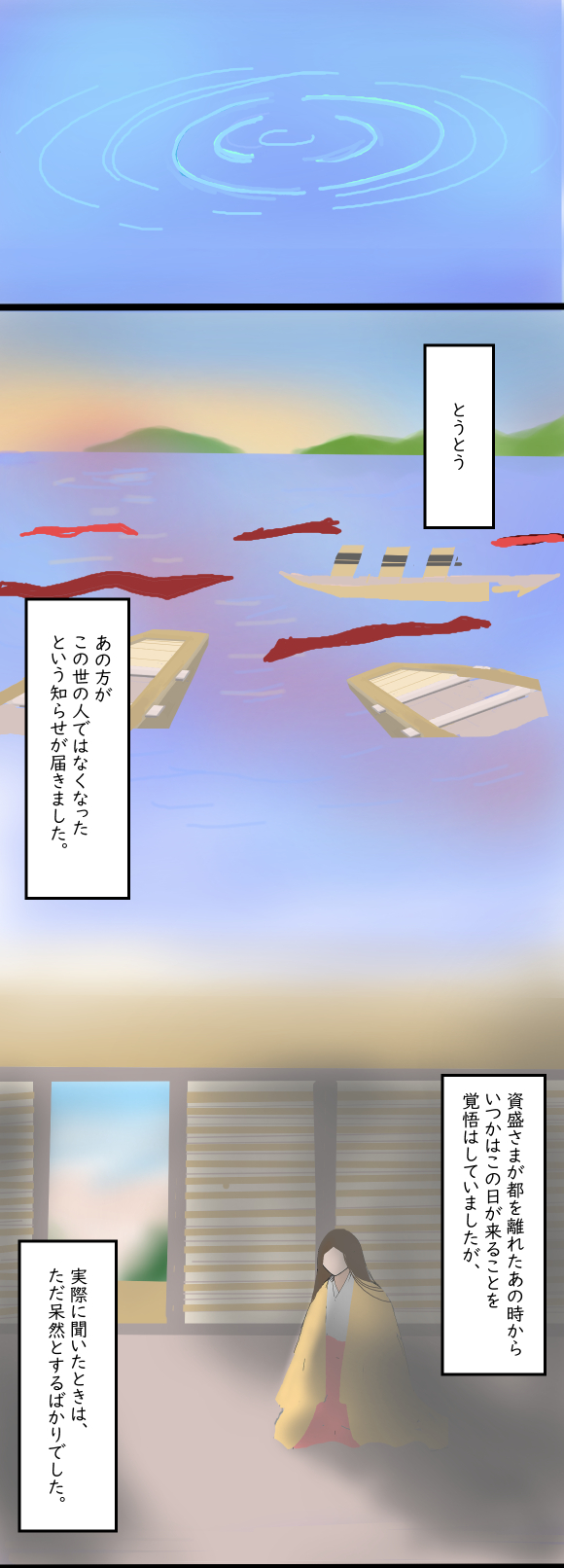
みな負けて逃げてしまった。

(2) 二 に 位 い 殿 どの はこの有様を御覧じて、日ごろ 思 おぼ し 召 め し まうけたる事なれば、 二位殿(= 平 たいらの 時 とき 子 こ )はこの 有様をご覧になって、日ごろから心構えをなさっていた事なので 、 鈍 にび 色 いろ の二 つ 衣 ぎぬ うちかづき、 練 ねり 袴 ばかま のそば高く挟み、 神 しん 璽 し を 脇 わき に挟み、宝剣を腰に差し、主上を抱きたてまつつて、 濃い灰色の二枚重ねの衣を頭にかぶり、練絹の袴のそばを高く挟んで(すそを上げ)、神璽を脇に挟み、宝剣を腰に差し、主上を抱き申し上げて、 「わが身は女なりとも、 敵 かたき の手にはかかるまじ。 続壇の浦夜合戦記(藤井純逍、三星社書房、昭和二十六年十二月、 発禁)• 能登殿は、大声で 「我ぞと思う者は近寄って、この私(教経)と組み合って、私を生け捕りにせよ。 (しかし能登殿は)判官(源義経)の顔をお見知りでないので、(身に着けている)武具の立派な武者を、判官かと見当をつけて駆け回った。

この他に 「日本の奇書七十七冊」(自由国民社、昭和五十五年七月、最新版は「日本の艶本・珍本 総解説」に改題)、 「地下解禁本」(小野常徳、KKベストセラーズ、昭和四十九年六月)に各々数編の解題と一部活字化がある。 新中納言知盛が味方の軍勢に下知をすれば、悪七兵衛景清は義経を小脇に挟んで海に投げ入れてくれようと息をあげる。
6
名前だけは聞いていた 『壇ノ浦夜合戦記』も詳しい内容が知りたかった。