忠度の都落ち

強調する意味があるが、訳す際に無視しても構わない。 しかし、1180年後白河上皇の皇子以仁王が、全国の源氏に平家打倒の令旨(りょうじ、命令)を出し、それに応じて源頼朝、源義仲らが挙兵しました。
13
強調する意味があるが、訳す際に無視しても構わない。 しかし、1180年後白河上皇の皇子以仁王が、全国の源氏に平家打倒の令旨(りょうじ、命令)を出し、それに応じて源頼朝、源義仲らが挙兵しました。
13
しかし、ここはどの意味か特定しがたい。 「る」は「受身・尊敬・自発・可能」の四つの意味があり、「自発」の意味になるときはたいてい直前に「心情動詞(思う、笑う、嘆くなど)・知覚動詞(見る・知るなど)」があるので、それが識別のポイントである。
18
世が鎮まりましたならば、勅撰集のご命令が出されることでしょう。
青葉に見ゆる梢には、春の名残ぞ惜しまるる。 「平家物語:忠度の都落ち(三位これを開けて見て〜)〜後編〜」の現代語訳 三位これを開けて見て、「かかる忘れ形見を賜りおき候ひぬるうへは、ゆめゆめ疎略を存ずまじう候ふ。
2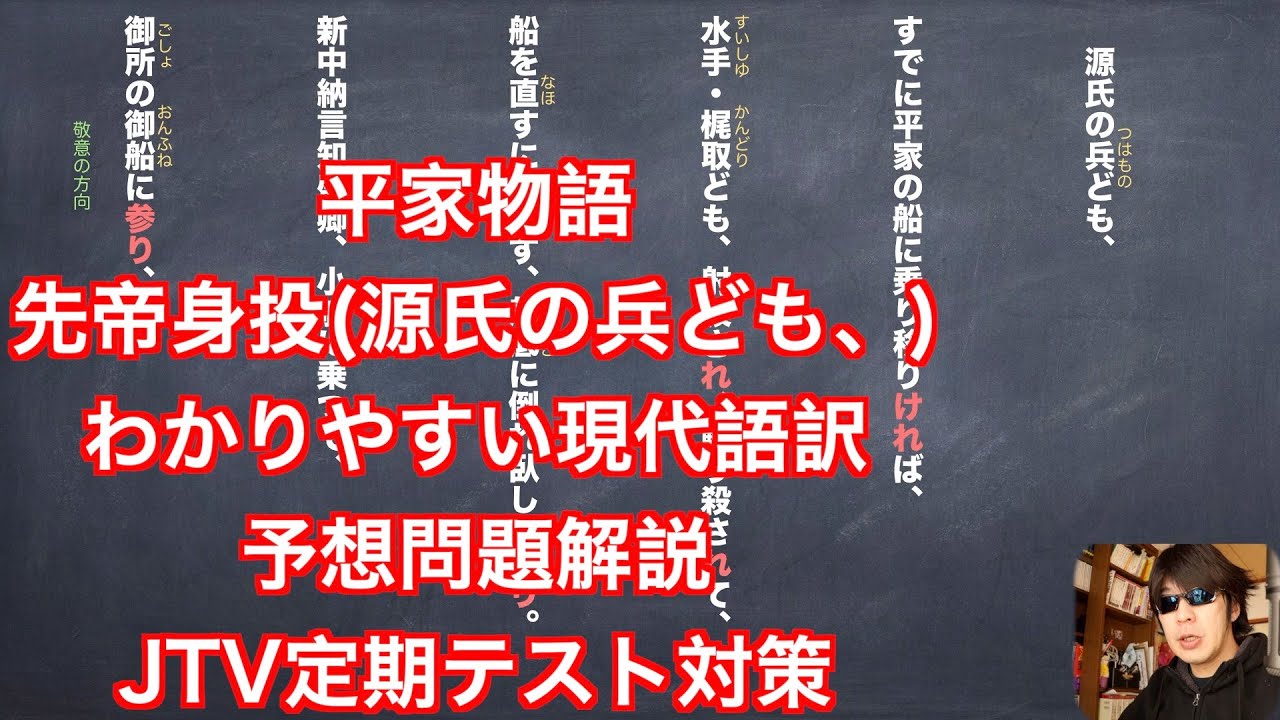
さい=サ行四段動詞「指す・差す(さす)」の連用形が音便化したもの ぞ=強調の係助詞、結びは連体形となる。 ず=打消の助動詞「ず」の終止形、接続は未然形 (あなたのこと/和歌の事を)おろそかには思っておりませんでしたが、いつも(あなたの)おそばに参上することもございませんでした。 「る・らる」には「受身・尊敬・自発・可能」の4つの意味がある。