電話リレーサービスとは?聴覚障害者なら絶対知っておきたい便利なサービスです!

この時からずっと150年以上もバリアが公共インフラである電話の中に存在していたことになります。 当初、TDDは非常に大型で紙に印字するものでした。
9
この時からずっと150年以上もバリアが公共インフラである電話の中に存在していたことになります。 当初、TDDは非常に大型で紙に印字するものでした。
9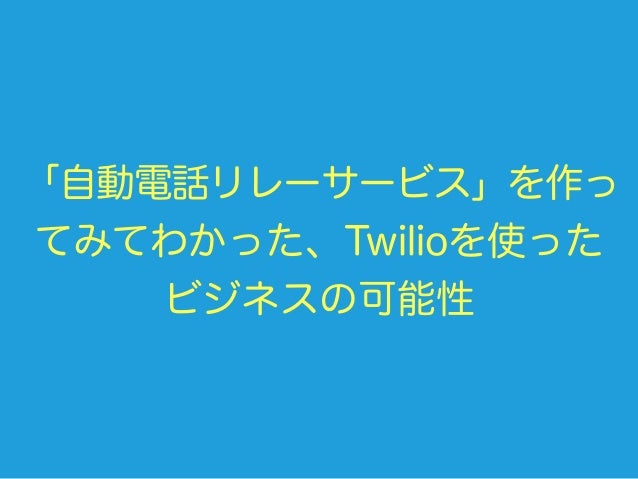
電話は、従来音声でやりとりをすることが前提としてあったため、法律・システム・制度などが、音声のみを使うことを想定されて作り上げられてしまいました。 利用するには事前のが必要になる 通訳オペレーターを間に挟むことにより、これまでは難しかった聴覚障害者の電話でのリアルタイムなやりとりが実現するのだ。 本ワーキンググループでの検討結果を受け法案の国会での審議が始まり、今年の6月5日に採決されました。
15
6月12日 金 、久松局長と倉野理事が「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案」の成立に際し、私たちの思いを国会で代弁いただいた議員の皆さまを訪問し、お礼を述べました。 足利銀行 手話通訳リレーサービスの着信には時間がかかる場合があります。 このような背景を踏まえて、聴覚障害者による電話の利用の円滑化のため、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの必要があることから、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、令和2年12月1日に施行されました。
18
2021年1月現在では、日本には公的な電話リレーサービスは存在しておらず、日本財団が制度化を目的とした「」という形で利用期間・時間・使用者数に制限をつけた試行サービスを提供しているのみです。 しかし、 何度もやり取りする必要があり時間も掛かるメールやFAXと違って、 即時に伝えられる電話は本当に便利で相手にも負担を掛けません。 写真:GBALLGIGGSPHOTO また、石井さんは聴覚障害者の生活だけではなく、彼らを支える手話通訳にも目を向ける。
8
手話通訳の世界は横の繋がりがあまりないそうで、今後養成カリキュラムなどを作成し、担い手を増やす必要がある。 ただ、2020年6月に電話リレーサービス法律案が可決され、今後24時間体制になるなどが可能になりました。
6
2021年7月から公的インフラ化し、。 羽田空港(東京都)に設置されている「手話フォン」 電話リレーサービスとは、聞こえない人と聞こえる人を電話リレーサービスセンターにいる通訳オペレーターが「手話」や「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につなぐサービスです。 ひとつは理解を広めるためのセミナー・講演の実施。
13