奥の細道(おくのほそ道)【ざっくり3分で解説】

古人も多く旅に死せるあり。

古人も多く旅に死せるあり。
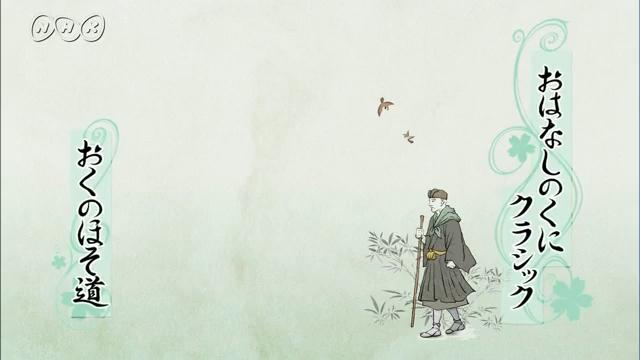
(たびだち) 弥生 やよい も末 すえ の七日、あけぼのの空朧々 ろうろう として、月はありあけにて光おさまれるものから、富士 ふじ の嶺 みね かすかに見えて、上野 うえの ・谷中 やなか の花の梢 こずえ 、またいつかはと心ぼそし。
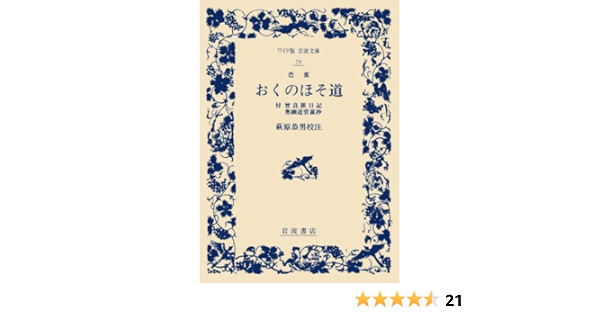
僕の心はまったく異なるものを求めていたのだ。 あやめふく日なり。 こちらが初案であろう。

旅に出るように誘惑する神様。 しばらくは 瀧 たき に籠 こも るや 夏 げ の初 はじめ (なす) 那須 なす の黒ばねといふ所 ところ に知人 しるひと あれば、これより野越 のごえ にかかりて、直道 すぐみち をゆかんとす。
6
(ひらいずみ) 三代 さんだい の栄耀 えいよう 一睡 いっすい の中 うち にして、大門 だいもん の跡 あと は一里 いちり こなたにあり。
19旅のなかに理想を見る彼の姿勢は、この後、生涯変わりませんでした。 江戸の月は、松島のつきの種を貰ってきて蒔いて育った実生のようなものに過ぎないと詠んだ句「 」がある。 この国の鍛治 かじ 、霊水 れいすい をえらびてここに潔斎 けっさい して劔 つるぎ を打 うち 、終 ついに がっさん と銘 めい を切 きっ て世に賞 しょう せらる。
3
東北旅行という現実の旅を終えた後、あらためて心の中で再構成した、いわば「心の旅」である。