分かりやすい精神科用語辞典3☆トークンエコノミー法
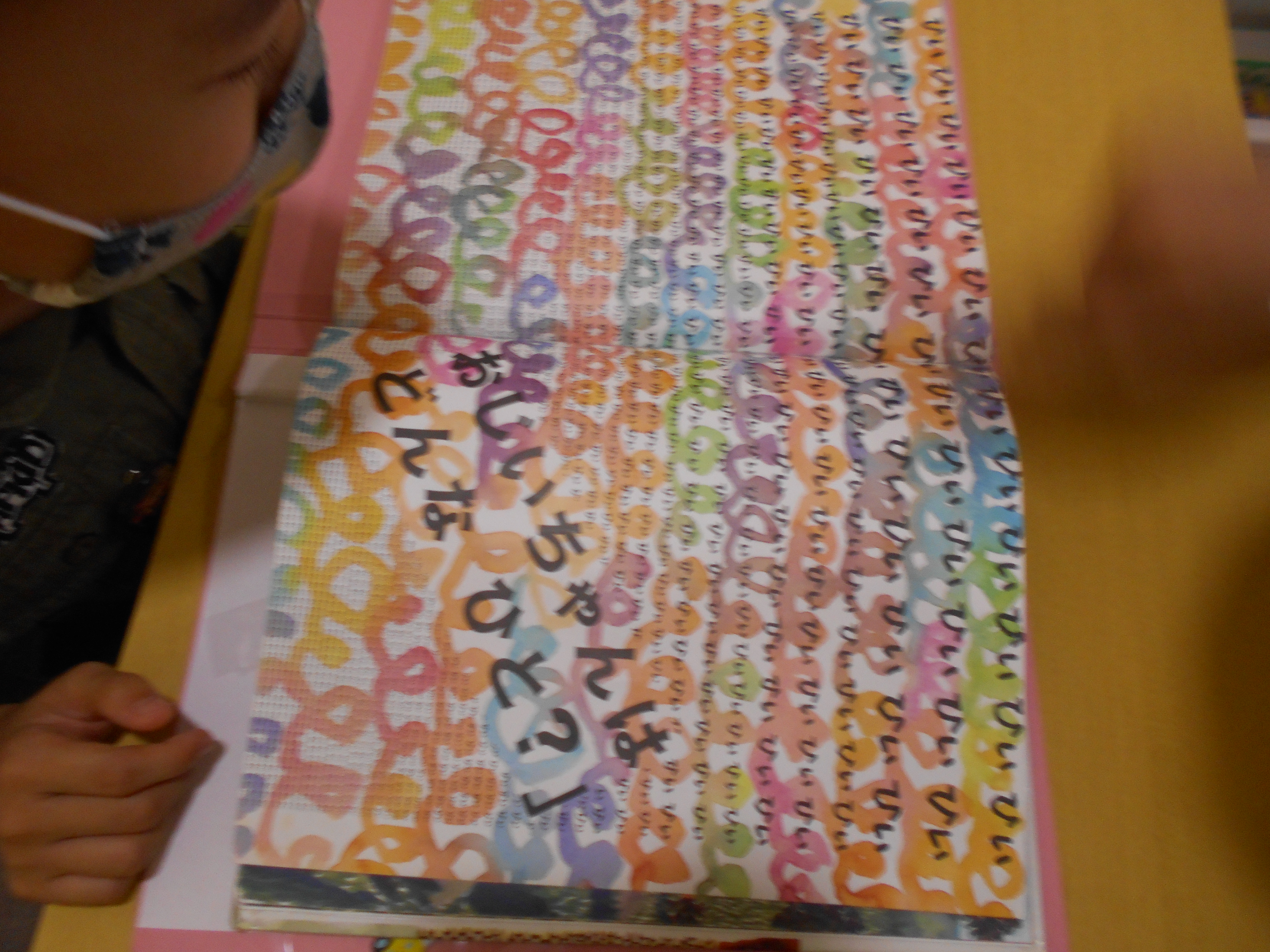
そのため、セラピーセッションでも、 「なぜこのような症状が出るのか、」 「なぜこのような不適切な行動を取ってしまうのか」 という事をクライアントに 洞察させる事は重視せず、 外的な条件を変えようとします。 行動形成法には• 色々と学術論文も出ているれっきとした専門用語であり、こちらの方が歴史が古く、1970年頃の論文のタイトルにも利用されている。 しかし実際は、 他の状況によって一般化が難しい と言う問題があります。
7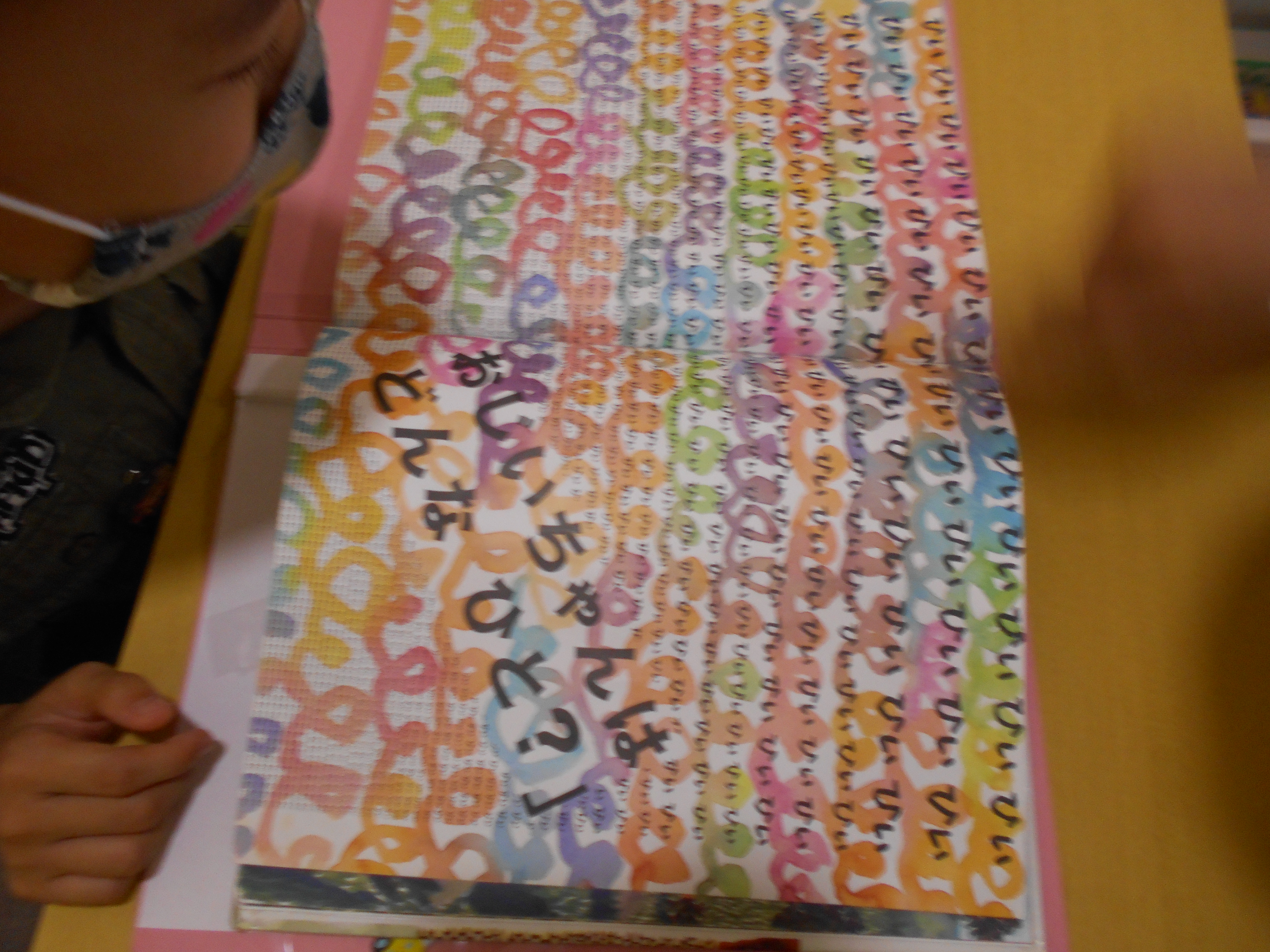
そのため、セラピーセッションでも、 「なぜこのような症状が出るのか、」 「なぜこのような不適切な行動を取ってしまうのか」 という事をクライアントに 洞察させる事は重視せず、 外的な条件を変えようとします。 行動形成法には• 色々と学術論文も出ているれっきとした専門用語であり、こちらの方が歴史が古く、1970年頃の論文のタイトルにも利用されている。 しかし実際は、 他の状況によって一般化が難しい と言う問題があります。
7
各都道府県でトークンを発行し、地域活性化を目指そうというアイデアです。 用語:• 標的となる適切な行動とトークンが得られる基準,バックアップ強化子の種類と交換できるトークン数を明確にし,視覚的に分かりやすいように工夫して,こどもにシステムを説明します。
13
望ましい行動が定着した後に継続し続けてしまうと、アンダーマイニング効果が起こる可能性がある。

フラッディング法• まずは気軽に。 ADHD・自閉症などの発達障害の子どもの状況にあわせて、うまくトークンエコノミー法を取り入れることで、子どものやる気やモチベーション、責任感や自信を育てることができることでしょう。
3
トークンは学校運営にも有効であり,トークンなどの具体物を用いた強化子のほうが,微笑みとか賞賛といった社会的強化子よりも効果的であり,有利であるという報告もあります。
6
最初はシール2枚たまったらバックアップ強化子と交換するなど,頻繁にバックアップ強化子と交換する機会を作り,システムの意味を教えていきます。
15